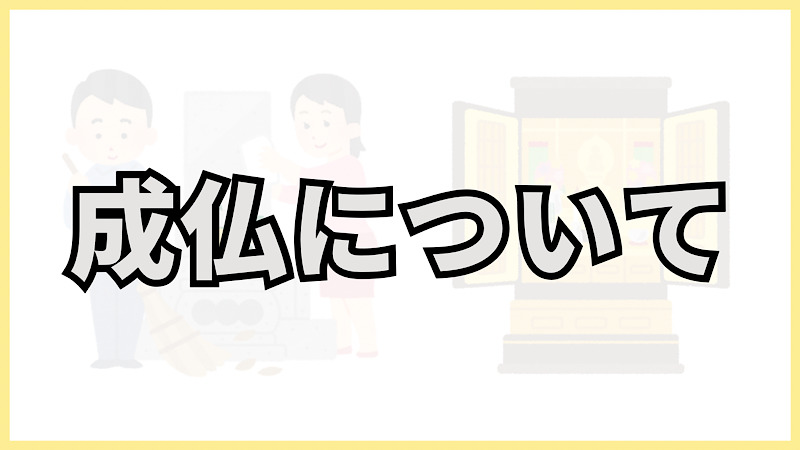

こんにちは、識子さんファンのシンタロウです。
このブログでは、桜井識子さんから神仏を学び、人生を豊かにする方法を共有しています。

- 成仏について知りたい!
- あの人はちゃんと成仏できているのだろうか?
以上のような、成仏について知りたい方のご要望にお応えします。
この記事について
・成仏についてのあれこれをまとめています。
※個人的見解で書かれたものをまとめています。宗教・宗派などの教義と異なる、お坊さんやお寺の関係者の方々とは意見が違う、などあると思いますが、そこのところをご理解のうえでお読みください。
成仏について
まず「成仏」とは何なのかですが、辞書などには、①「悟りを開いた状態」であったり、②「死んで、この世に未練を残さず仏になること」と書かれています。
こちらの記事で扱う「成仏」とは、②に書かれていることを指します。しかし、「仏になる」とは、如来や菩薩のような仏様ではありません。意味合いでいうと、ご先祖様になります。
※亡くなった方の「成仏」を考える人がほとんどだと思いますが、自分が死んでしまった時にちゃんと「成仏」できるか、という視点で見ていただくと理解と興味が深まるかと思います。
詳しくはこちらの書籍に書かれています。
このまとめ記事の内容をもっと知りたい方にオススメです。
亡くなった方がちゃんと成仏しているのだろうか?したかどうかわからない。。。また、成仏しない(できない)とどうなるんだろう?と気になっている人はたくさんいると思います。
がその前に、亡くなるまでがどうなのかというと、
・亡くなる直前の状態は
これは自分が亡くなる時もそうらしいのですが、
・亡くなる前に魂が抜けて、自分から会いたい人に挨拶に行ける
最後に会っておきたい人には挨拶に行けるシステムになっているそうです。亡くなる前に意識不明の状態が続いている時は、その間に挨拶に行っていることもあるようです。(魂が挨拶に来たら、識子さんにはキラキラ光る物体が見えるそうです)
ですので、死に目に会えなかったという人がいても、実は故人は会いに来ているそうです。
「神様へのご挨拶」も亡くなる直前に
もうひとつ大事なことは、
・死んでしまったら神様には会えない
神様が大好きな人は、亡くなる直前に神様にご挨拶に行かないと、その後はかなりの時間が経たないと会えなくなります。(亡くなった後の世界と神様の世界はリンクしていないため)
神様には「生きている今だから」自由に会うことができるのだそうです。
ですので、今世でお世話になったお礼は、亡くなる直前の魂の状態で言いに行くことができます。魂なので日本中を自在に行けて、時間の感覚も違うので数秒でも参拝した全ての神社に行くことができます。(三十三間堂で手を借りていたら、返すのもこの時です)
自分から行かないと、誰も連れて行ってくれないので、覚えておきましょう。
また、亡くなる瞬間は「自分の一生」を見ているそうで、自分の歩みを振り返る「崇高」な瞬間です。
亡くなる場所や誰がいるかなどは頭にありませんので、「場所は自宅が良かったのでは」とか、「独りで逝かせてしまって申し訳ない」などの後悔を抱いてしまうと、故人が胸を痛めてしまいますので、後悔は手放すことが大切だそうです。
・亡くなった後は
故人は亡くなった後は、49日間は地上と重なる世界にいます。その後に成仏していきます。49日が経過する前に自力で成仏する人もいれば、49日の法要でお坊さんのお経を助けにして成仏する人もいます。(後者がほとんどです)
※亡くなっても、生前と同じように自分の肉体があるように見えるそうです。ですので、事故などの場合は、自分が死んだことに気づかないこともあるようです。
生前に馴染みのある宗教で供養する
結婚したことにより宗教が変わり、その宗教で供養(葬儀)をした場合に、成仏できないこともあるようです。
》供養について 後編
※49日の法要では、その場に故人の位牌か遺骨が無いと、お坊さんの読経が届きませんので、成仏の助けにはなりません。ご注意ください。
》不思議な縁のお話
もしも故人が見えたら
49日の間に、霊として故人の存在が見えることもあるそうです。その時は、見た人によって故人の服装が違ったりします。その人が持つ故人の印象だったりが影響するようです。
また、49日の間に故人を夢で見るというパターンが一番多くあるそうですが、ほとんどが
・「今から成仏するよ」
・「成仏したから安心してね」
という成仏のお知らせだそうです。突然の死などで挨拶に行く余裕がなかったからのようです。(成仏した証拠・証明になるかもしれませんね)
夢での故人が、「笑顔でこちらを見ている」「美味しそうに何かを食べている」などが見えた場合は、自分の魂が「成仏したよ」のメッセージをこのようなものに変換していることがあるようです。
※まれにですが、別のメッセージの場合もあります。その場合は伝えようとしていることがなんとなくわかるそうです。
豆知識
葬儀の時などに遺体に接すると、人間の「生気」は少なからず影響を受けるようです。
生きるエネルギーを消耗するらしいのですが、黒の喪服を着ることで、エネルギーの消耗をほとんど受けなくなるそうです。
》神様の黒い服とは
・成仏しないと幽霊のままになってしまう
何かにこだわっていたり、悪い状態にいると49日を過ぎても成仏することが難しくなるようです。また、単純に成仏の仕方がわからないという幽霊もいるようです。
この世に心残りがあると成仏が遅れてしまう
亡くなった母親が、子供が心配で成仏しないまま家の中に留まっているというエピソード。(成仏した方がそばにいることができて、残してきた人を守れると説得されています)
》成仏することを知る大切さ
例え誰かのためにそばにいたいと思っても、幽霊のままだと、波動が低いので障りを与えてしまいます。成仏したほうが良いのです。
自ら成仏しないことを選んでいる幽霊
外国には、生まれ変わって高貴な身分ではなくなってしまうのを避けるために、成仏しない選択をしている幽霊がいます。
他に、幽霊に関してはこちらにまとめています。
》【幽霊・霊について】まとめました。
ちゃんと成仏するためには
人はいつかは亡くなります。亡くなった後に、無事に成仏するために、いくつか知っておくと良いことがあるようです
・三途の川
「三途の川」というのは実際にあるようで、仏教などの宗教観とは関係なく、川の存在を知らない人でも行くことがあるそうです。
なのですが、実は、
・三途の川を「渡る人」と「渡らない人」がいる
厳密に言うと、三途の川がある場所に行く人と行かない人がいるそうです。なぜ行く人・行かない人に分かれるのかは定かではありませんが、
行く人は、川を渡らないといけません。川を渡らないと「成仏が遅れる」ことになるようです。渡るには川の中を歩いて渡ったり、船に乗せてもらって渡ることができるようです。(高齢で亡くなっても肉体的な年齢は関係ないので、歩いたり泳いで渡ったりできるそうです)
自力で渡る人は問題ないのですが、濡れたくないからと船に乗せてもらって渡る人は、渡し賃として「お金」が必要になることもあるのだそうです。
なので生前に、お葬式の時には「棺にいくらかのお金をいれてもらう」ようにお願いすることがあります。(いくらかは本人の考え方次第で、金額が決まっているわけではないそうです)
本人の考え方次第では渡し賃の「お金」が必要かも
知っておいた方が良いことは、川を船で渡るための「考え方」が重要だということで、自分がどう考えているかで変わるようです。
服や靴にこだわりがある人は「濡れたくないから船に乗る」と考えます。この時に「船に乗るのにお金が必要だけどお金を持っていない」と考えてしまうと、船に乗れなかったり、船が来なかったりするようです。
「船には乗るけどお金は要らない」や「ただで乗せてくれるでしょ」と考えていたり、生前から「渡し賃に○○円が必要になる」(金額は遺族ではなく本人の考え)と考えていて、お葬式でその金額を棺に入れてもらえれば、船に乗せてもらえます。(棺にコインは入れてはいけないそうです)
・お金がないのと、濡れたくない念が強くて三途の川を渡れない幽霊のエピソード
》現代版幽霊

三途の川は自力で渡れるし、濡れてもすぐ乾く!と覚えておきましょう
ちゃんと納骨をする
遺骨はちゃんと納骨した方がいいようです。形見として持っておきたいという人もいるかもしれませんが、良いことではありません。(持っておきたい人の意思は尊重すべきですが、遺骨を加工してペンダントなどにして身につけるなどは、波動の観点から考えると良くないそうです)
少量の遺骨(加工したものでも)、遺髪、遺歯、を持っていてお返ししたいという場合は、お墓に入れるか、お寺で処分をお願いします。
どちらも無理な場合は、海か大きな川に流します。(少量の場合です)
手順としては、まずお地蔵さん(空海さんでもいいかもしれません)にご縁をいただき、真言を授かります。
海(川)に流す前に、お地蔵さんの真言を何回か唱えて、お地蔵さんに来てもらい、事情を説明してお願いをして流します。
お墓以外の場所(山の中など)に埋めたり、ゴミとして捨ててはいけません
持っている人がいても
遺骨を持っておきたいと思う人もいらっしゃると思うので、その人の考えは尊重します。
そのうち、「納骨した方がいいかな」とか何か納骨するキッカケや感じることが出てくるようです。
他に、生きている間に切った髪の毛は「遺髪」ではありませんし、生きている間に抜けた子供の乳歯も「遺歯」ではないので問題ないです。
年忌供養
特に年忌供養はちゃんとしたほうがいいそうです。1、3、7、13、17、(23)、25、(27)、33、(50)回忌など、宗派によって多少違います。
成仏のエピソード
・お墓参りで蝶が寄ってきたら、故人から「成仏しているよ」「供養をありがとう」というお知らせです。返事をしてあげると喜ばれます。成仏しているので、神仏寄りの霊的な虫の蝶を使うことができます。しかも蝶を使えるということは、力があり高い位置で成仏している証拠だそうです。(トンボも蝶と同じ)
》お墓参りと蝶
・成仏するには、自分の身の周りの空間のどこかに光が見えるそうなので、そこへ向かって行くといいそうです。光は米粒くらい小さかったり、遠くにあったりするので、見当たらない場合は隅々までくまなく探さないといけません。(成仏する準備が整うにつれて光が大きくなるそうです)
》網走監獄
》気の毒な幽霊をなんとかしてあげたい
・識子さんが小さいころ、亡くなったお祖母さんに伝言を頼まれたお話
》祖母のお葬式で学んだこと
個人でできる供養について
識子さんのブログにある、供養の仕方であったり、こういうことが供養になりますよ〜と書かれているものをまとめていきます。
供養の効果が意味を持つ期間(この表現が適切かわかりませんが)には2つあるようで、①成仏するまでの期間と、②成仏して50回忌を迎えるまでの期間に分かれるようです。
①は、成仏が難しい状態の人(自殺など、すぐには成仏が難しい状態があります)がちゃんと成仏するための供養で、亡くなった方を癒して、成仏に導く手助けになる効果があります。
②は、成仏して50回忌の先に進むためのサポートになる供養で、重要なのは年忌供養ですが、下記にまとめている供養も効果があります。(詳しくは書籍を読まれてください)
・写経について
ブログに最もよく出てくる供養である「写経」についてです。「写経」供養は人間だけができる「人助け」だそうです。
「写経」とは、もともと仏教の経典を書き写す、または書き写した経典のことをいうそうですが、供養のためにする「写経」は『般若心経』を書き写します。
写経はサポートになる
亡くなった方を思いながら心を込めて書いた「写経」は、優しく癒す、愛のある供養となり、亡くなった方のサポートになります。
ここで大事なことは、
・仏様(お寺)に奉納しなければ、供養は届かない
お寺で書いたものは、そのままお寺に奉納すればいいのですが、自宅で書いた場合は、お寺に持っていくか、郵送するかして、奉納しなければ供養が届きません。(金剛峰寺や奈良県の薬師寺などは郵送を受け付けているそうです)
写経に関してのいろいろ
・写経を送る相手の宗教は関係ない
写経は仏教ですが、供養の効果は「国籍」「宗教」「どこに住んでいたか」など関係なく、どの人にも作用します。有名人や会ったことがない人など、面識がなく一方的に知っている人でも大丈夫です。
・「為」の書き方
供養のための写経では、「為」のあとは戒名であったり姓名を書きますが、複数の人を書いてもいいですし、「〇〇で亡くなった方々」と書いても大丈夫だそうです。(その場合は、供養が人数分に分割されるようです)
「ご先祖様」へ書く場合は、「為」にそのまま「ご先祖様」と書けば大丈夫です。「父方」「母方」や「お墓」「仏壇」など別だとは考えません。(法要などの場合は、お寺や宗派に従います)
「為」の部分に「仏様のために」や「写経供養を必要とする人のために」と書くと、供養は必要な人に使われるので、どこかの誰かを救うための尊い写経になります。自身の「徳を積む」ことになります。
※「為」が無い用紙の場合は「自分で書く」か、仏様の前であれば「誰に送るのか」を伝えると届けてもらえます。
・仏様がちゃんと届けてくださる
亡くなった人は、仏様の世界に存在する鬼籍(過去帳)に名前が載るそうです。仏様世界のことなので、鬼籍に名前の載った人のことは、すべての仏様が把握しているそうです。どの仏様に写経を奉納しても、供養を届けてくださいます。
・写経する場所は、お寺で書いても、お家で書いても、そこまで差はない
お寺で書いた方が思いは入りやすいのですが、そもそも写経自体が、お経に「思いを載せる」という行為だそうです。お経の力で思いを込めており、お経がメインであるため、差はないそうです。
・お墓参り
お墓参りは故人にとって嬉しい供養のひとつです。他にも、いろいろな方法で供養のパワーを送ることができます。
仏壇やお墓で般若心経を唱える
お墓参りなどで、般若心経を唱える(CDを流す)ことで、さらに喜んでもらえます。(宗派は問わない)また、年忌供養でどうしてもお坊さんにお経をお願いできない場合、CDの法要でも少しだけ助けになります。
》「神仏をいつも身近に感じるために」 CD発売のお知らせ 説明その②
》奉納についてとCDの補足
識子さんのCDに関しては
》識子さん監修の「CD」の使い方・効果(まとめ)
生花
生花には「供養パワー」があるそうです。お墓や仏壇にお供えすると喜ばれます。(野に咲いてる小さな花などでも喜ばれます)
》仏様へのお供え物
恐山へ会いに行く
会ったことのないご先祖様でも会えるそうです。
》お財布術
恐山については「死んだらどうなるの?」に書いてあります。
愛の感情を送る
愛や感謝の「感情」を送ると良いそうです。言葉よりも、楽しく過ごした日々を思い出して送ります。「亡くなって悲しい、つらい」などの悲しみや心配の念を送らないように気をつけます。
》恋愛のパワースポット
位牌やお墓がない場合は
仏様の前で、その故人(名前など説明します)の位牌やお墓が無いことを仏様にお伝えし、愛や感謝の感情を思い出し、故人に届けてもらうようにお願いします。(仏様への”願掛け”という形になりますが、必ず叶えてもらえます)
》位牌もお墓もない方の供養

いくつが供養の方法があるので、ちゃんと成仏させる・させたいと思っておられる方の参考になればと思います。
ご先祖様について
成仏した故人は、現実世界の仏壇にいるのではなく、あちらの世界に存在しているそうです。位牌・お墓は成仏した人が「顔を出せる」場所であって、常にそこにいるわけではありません。
普段はあちらの世界から子孫を守っています。
お供えは、個人が好きだった飲み物やお茶が良いようです。(「水」を欲しがるのは成仏していない幽霊だけです)
・お盆に帰ってくるご先祖様
ご先祖様は、年に1回のお盆に、現実世界に帰ってくることができるようです。位牌などから顔を出すのではなく、自分自身の体ごと帰ってきます。
※亡くなって49日の間の成仏していない故人は、現実世界と重なる世界(幽界)にいて、すぐそばにいます。
家の中に帰ってきている
ご先祖様はあちらの世界から、しっかりとした存在として家の中に来て滞在するそうですが、亡くなった人の全員が帰ってくるわけではありません。50回忌を超えた人(魂)は成仏界の向こう側に進むそうです。
※親しい家族がいない、帰る家がないという人も帰ってきません
・ご先祖様が喜んでいる時
お盆やそれ以外の時でも、仏壇にロウソクを灯すことがあると思います。
この灯明している時に、ロウソクの炎がシューッと伸びることがあるのですが、その時は、
・ご先祖様が喜んでいる
もちろん、風が吹いて伸びることもあるので、全てがそうとは言えませんが、ロウソクが伸びた時は、ご先祖様が「ありがとう」を伝えているのかもしれません。
仏様のごりやく
・薬師如来さんは愛する人やペットを失った悲しみなど、心のケアをしてくださいます。
》心も治す薬師如来様
・事故の現場にお地蔵さんの石仏(亡くなった人のための)を作ったら、その石仏とお地蔵さん(仏様)とをつなぐ道ができた時に、その(波動の高い)道の作用で成仏できるそうです。
》猫地蔵尊
仏様との会話
・穏やかな心でいると、亡くなった時に成仏しやすい(阿弥陀如来さんとの会話)
》浄瑠璃寺
追加情報(2023年9月以降のブログから)
・自分が亡くなった時にちゃんと成仏するため(幽霊にならないため)には、「すべてを手放すこと」だそうです。「あれがやりたかった」「あのことが心残り」のような念を持ったままだと、成仏が難しくなるそうです。
》幽霊にならないようにする方法
・幽霊になったままのおじいさんを説得されたエピソード
》意外と早かった203のおじいさんの成仏
・火葬する前に棺に入れたものは、ちゃんとあちらの世界に持っていける
信仰心の薄い人でも問題なく持っていけるそうです。また、洋服などは入れなくても、故人が自分で選んだ姿を見せれるようです。
》亡くなった人に持たせてあげたいもの
他に参考にしたブログ

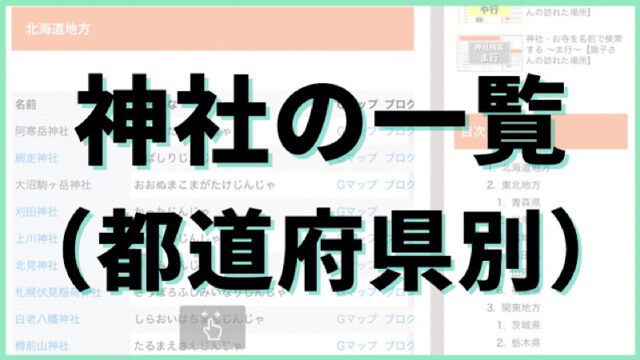
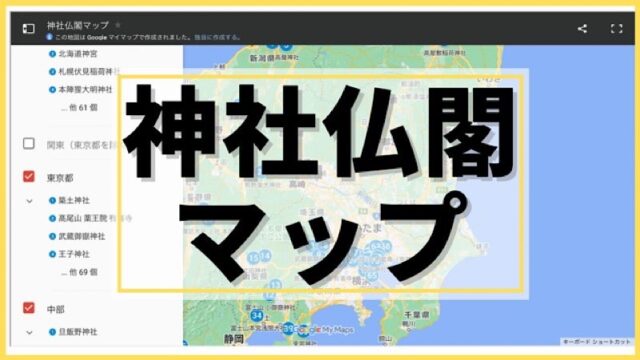
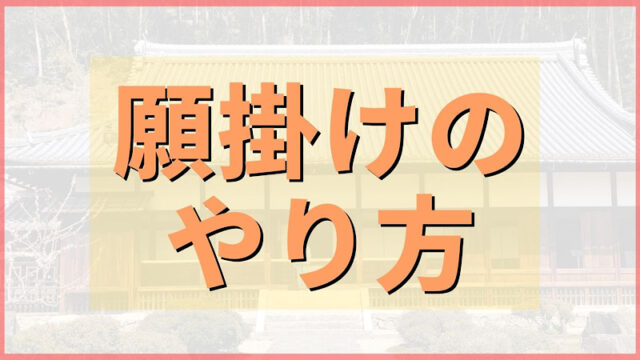
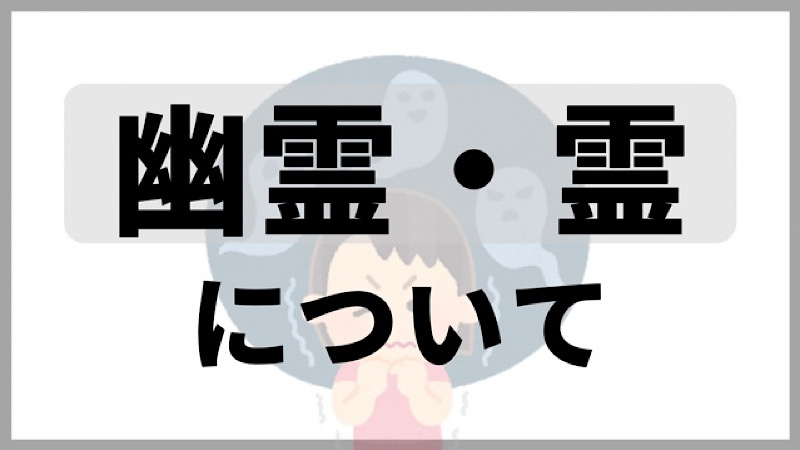
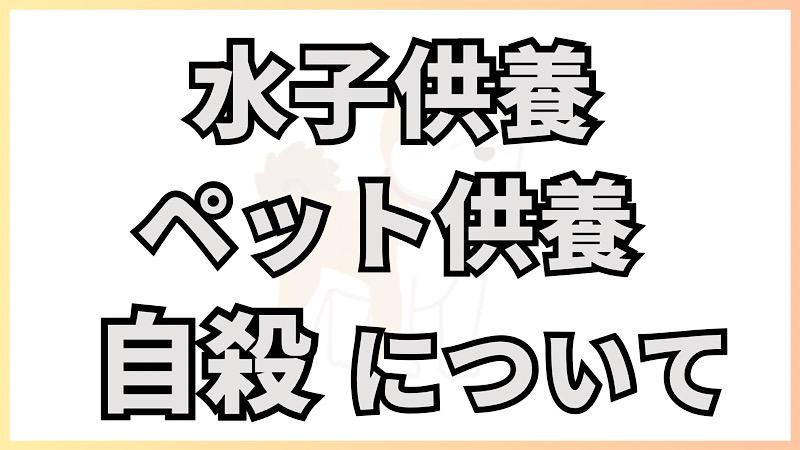
熊本県在住 30代 男性
識子さんファン歴9年目
たまたま識子さんのブログを発見し、神様・仏様のありがたさに感動する。熊本在住なので、北の方にある神社仏閣に行きたいな〜と思いながら過ごしている。
〈所持〉
識子さんの本26冊くらい
縁起物21個くらい
〈五芒星〉
・宮地嶽神社
・箱崎八幡神社
・宇佐神宮
・祐徳稲荷神社
・大御神社
〈五芒星2〉
・加藤神社
・別所琴平神社
・藤崎八幡宮
・北岡神社
・健軍神社